京都府知事挨拶

京都府知事
西脇 隆俊
2023年度日本建築学会大会が、盛大に開催されますことをお喜び申し上げます。本大会は、明治23年の第1回大会開催から120年以上の歴史があり、京都での開催は昭和34年以来64年ぶりとなります。全国各地からお集まりいただく皆様を心から歓迎いたします。
日本建築学会の皆様におかれましては、明治19年に設立されてから今日まで、我が国の建築界を先導されるとともに、建築に関する学術・技術・芸術の進歩・発達に多大な御貢献をいただいております。
これもひとえに、竹内会長をはじめとする歴代の会長や役員の皆様、会員の皆様の永きにわたる御尽力の賜物であり、心より敬意を表します。
今大会は「歴史がひらく未来」をメインテーマとして開催されます。悠久の歴史を有する京都におきまして、今年は、文化庁が移転し、「文化の都・京都」の実現に向かって新たなスタートが切られました。さらには、今後、2025年の大阪・関西万博の開催や新名神高速道路の開通が控えているところであります。このような京都の地において、本大会が開催されますことは大変意義深いものであると考えており、皆様には「建築のこれから」について探求していただければと心から願っております。
京都府では、今年度から、「安心」「温もり」「ゆめ実現」の3つの視点による「あたたかい京都づくり」に向けた総合計画をスタートさせておりますが、本計画が目指す、安心・安全の確保やまちづくりの進展、文化の創造にとって、建築物はなくてはならないものであります。新たな時代の京都を築くため、皆様との連携を一層深めてまいりたいと考えておりますので、変わらぬ御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本大会の成功と日本建築学会の今後益々の御発展、そして参加される皆様の一層の御活躍を心よりお祈り申し上げます。
京都市長挨拶

京都市長
門川 大作
「2023年度日本建築学会大会(近畿)」の御開催を、心からお祝い申し上げます。
3年以上にわたるコロナ禍を経て、対面での開催は実に4年ぶりと伺っています。かつての日常が戻りつつある中、開催に御尽力の竹内徹会長、谷口徹郎委員長、西山峰広実行委員長をはじめすべての関係者の皆様に、深く敬意を表します。
我が国の建築界の発展に、かけがえのない役割を果たしてくださっている貴学会の皆様は、建築はもちろん、複合災害に対する備えや2050年脱炭素社会実現、DXの推進など、幅広い分野で先を見据えた取組を力強く進めてこられました。
貴学会については、1998(平成10)年に「京都の都市景観特別研究委員会」を設置。4年間の御検討を経て「京都の都市景観の再生に関する提言」を提出くださいました。その内容は、建築物の高さ規制、屋外広告物対策、京町家の保全など、本市の「新景観政策」の推進、新たな景観づくり等々に大きな役割を果たしたところです。この場をお借りして、改めて心から感謝申し上げます。
さて、京都の都市格の向上に重要な役割を果たした「新景観政策」の施行から16年。本市では今春、景観の骨格を守りつつ、活力のあるまちの実現に向け、都市計画の見直しを行いました。暮らしの豊かさや利便性につながる都市機能の集積・充実、さらには、若者・子育て世代が「京都で住みたい、学びたい、働きたい、子育てしたい」と思える魅力的な空間の創出へ。まさに、持続可能な都市の実現に向け、市民等の皆様の御理解の下、新たな挑戦をスタートさせました。
同時に、機能強化された「新・文化庁」が京都に移転し、5月には本格的に業務がスタート。京都が名実ともに「文化首都」となる画期的な出来事を、心から嬉しく思うと同時に、その責任の重さを痛感しています。日本各地に息づく多様で豊かな文化に光を当て、地方創生をつなげていこうと、決意を新たにしています。
こうした中、「歴史がひらく未来」をテーマに開催される本大会。空間を作る営みである「建築」の未来に向けた自由闊達な御議論は、未来の京都、引いては日本全体のまちづくりに大きく寄与するものと確信しています。
本市といたしましても、貴学会の皆様のお力をいただきながら、京都の強みを最大限に活かした取組に、引き続き全力を尽くす決意です。変わらぬ御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、本大会の御成功と、貴学会のますますの御発展を祈念いたします。
京都大学総長挨拶

京都大学総長
湊 長博
2023年度日本建築学会全国大会(近畿)が1959(昭和34)年以来、実に久方ぶりに京都大学で開催されますことを大変喜ばしく、心からお祝い申し上げます。
日本建築学会は、1886(明治19)年に創立され、その会員数は今や3万6千人余を数え、由緒ある工学系学会として長年歩みを進めてこられました。新型コロナウイルス感染症が完全に終息しない中で、今年も一部オンラインを併用しつつも、3年ぶりに対面を基本とした全国大会に際して、多くの皆様を京都にお迎えできることを非常に嬉しく思います。
京都は、「日本近代土木工学の父」といわれる田辺朔郎博士ゆかりの地です。田辺博士は、1883(明治16)年に工部大学校(後の東京帝大工学部)の土木工学科を卒業、後にイギリス土木学会テルフォード・メダルを受けることになる卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」によって時の北垣国道京都府知事に請われ、1890(明治23)年琵琶湖疏水の大工事を完成させました。その後日本初の水力発電所など多くの国家事業に関わり、若干39歳で京都帝大教授に就任、その後同工科大学長を務められました。琵琶湖疏水は130年以上経った現在も京都市民の重要な水源であると当時に、蹴上発電所などの施設は、その精緻で美しい様式によって観光名所としても親しまれています。
本大会のテーマは「歴史がひらく未来」です。建築は計画、設計、構造、環境、生産、材料、防災など幅広い分野が統合された総合的な学問です。歴史都市を代表する京都の地で、個別科学の技術や学術領域を超えた知の融合を通じて、これまでの歴史を踏まえより豊かな未来社会の実現に向けて、現代の複合的な課題解決に挑戦できるようなイノベーションが創出される大会になることを願っております。
最後になりましたが、本大会の開催にあたって、ご尽力くださいました各界の皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。また4日間に亘る期間中、活発な学術交流・情報交換が行われ、皆様にとって実りあるものとなりますよう祈念し、私の挨拶に代えさせていただきます。
日本建築学会会長挨拶

日本建築学会会長
竹内 徹
日本建築学会は、建築に関わる学術・技術・芸術について、その発展を図ることを目的として1886年(明治19年)に創立され、今年2023年で137年目を迎えます。会員数は約3万6千人を擁し、我が国の工学系の学会としては最も長い歴史を持つものの一つです。社会貢献を続ける学術団体として活発に活動し、我が国の建築界においてつねにリーダーシップを発揮してまいりました。毎年開催される全国大会は、その最も大切な行事の一つであり、約1万人の会員が集い、総計7千題を超える学術講演、建築デザイン発表会、関連する多くのパネルディスカッションや研究協議会などが開催されてきましたが、2020年以来3年間、コロナウイルス感染症対策のため、オンライン開催やハイブリッド開催を余儀なくされてきました。今年はオンラインを一部活用しながらも、3年ぶりに個別の学術講演、建築デザイン発表会等が対面で実施されることとなります。講演発表される学生の皆さんにも久しぶりに日本中の研究者や先生方、他大学で同じテーマに取り組む学生の仲間の前で直接発表し交流する機会が与えられ、緊張感の中にも想い出に残る貴重な経験ができるものと期待します。
京都で開催される今年の大会のメインテーマは「歴史がひらく未来」です。開催概要に紹介されているように、京都の街並みは長い歴史とともにつくりだされ、人々の生活に浸透し、意味や文化の基盤となり、かつ未来に向かって変化していこうとする歴史都市です。感染症蔓延下の3年間、私たちは住まい方、働き方、学び方の多様性や意味について深く考えざるを得ない環境におかれてきました。その経験を踏まえ、成熟した地方都市がこれからどのように活気を維持し、若い人たちが喜んで住まい、子育てができ、美しくかつ災害に強い環境を整えていくのか、その建築・まちづくりに関する活発な議論を行っていただければと思います。そして何より久しぶりの「お祭り」を楽しみ、交流し、京都での想い出を作っていただければと思います。
2023年度日本建築学会大会(近畿)大会委員長挨拶

大会委員長
谷口 徹郎
今年の日本建築学会大会は、京都大学を主会場として開催されます。近畿での開催は、2014年に神戸大学を主会場として開催されて以来9年ぶりとなります。コロナ禍の状況が不透明な時期のお願いにもかかわらず、会場をお引き受けいただいた京都大学の皆様には心より感謝申し上げます。また、大会期間中も何かとお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
開催地である京都府、京都市には、知事ならびに市長に大会委員会顧問をお引き受けいただくなど多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。また、近畿地方の建築関係各団体の皆様を含めてご支援ご協力を賜りますこと、重ねて感謝申し上げます。
今回は、2019年の北陸大会から4年ぶりの対面での開催となりますが、この間の社会状況の変化は著しく、運営方法の見直しは必須でした。大会実行委員会には、運営方法の検討に多くの時間と労力を費やしていただきました。検討の結果、例えば、感染防止対策としても有効なキャッシュレス化を進めることになりましたが、これは会場におけるセキュリティの向上にもつながりました。また、特に遠方の方の移動に配慮して、コロナ禍を経て社会に大いに浸透したオンライン技術を一部取り入れております。
一方で、コロナ禍によって、対面で接することの大切さを再認識することとなりました。今大会では、学術講演発表は対面で実施されます。発表・質疑そのものは、オンラインでもある程度は事足りますが、発表間や休憩時間の会話、あるいは参加者の表情・雰囲気を感じるなど対面でしか得られないものも多くあると思います。今大会では、そのような出会いから多くの化学反応が起こるのではないかと期待しています。今大会が皆様にとって有意義な場になることを祈念しております。
2023年度日本建築学会大会(近畿)大会実行委員長挨拶
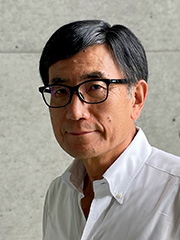
大会実行委員長
西山 峰広
日本建築学会創立4年後の明治23年の第1回から数えて、124回目となる日本建築学会大会が9月12日から15日の4日間にわたり京都大学で開催され、皆様をお迎えできること、大会実行委員会委員長として大変うれしく思っております。これもひとえに大会委員会顧問と委員、実行委員会委員、日本建築学会近畿支部と本部の皆様の尽力によるものと感謝申し上げます。
最近、近畿で大会が開催されたのは、8年前の神戸大学での開催になります。当時の準備状況を記憶している教員はほとんどおらず、ほぼ一からの出発となりました。ただし、日本建築学会近畿支部と日本建築学会本部にはこれまで行われてきた大会の蓄積があり、多くの情報と助言をいただくことができました。
2021年9月28日に第1回連絡会という形で実行委員会を立ち上げ、何回かの打合せを行った後、正式には2022年8月3日に第1回実行委員会を開催いたしました。2022年9月の北海道大会開催中に北海道大会実行委員会との情報交換会を開催し、さらに同9月京都大学吉田キャンパスにおいて対面で開催された土木学会大会を視察させていただく機会を得ました。このようにほぼ2年の準備期間により今大会が実現できました。
どのような開催形式にするか、対面かオンラインか、当初は議論がありましたが、基本的には対面で行うことが前提となりました。そうは言うものの、状況によってはオンラインに切り換えざるを得ないかもしれず、その際の対処方法も必要となります。特に、懇親会を行うのか、行わないのか、行うとしたら、着席か、立食か、懇親部会を中心に情報収集と議論を重ねました。幸い、5月8日に新型コロナの感染症法上の位置付けが5類感染症となり、これも対面開催への追い風となりました。
新型コロナがなくなったわけではなく、これからも警戒する必要があります。そのような中ではありますが、是非多くの方々に京都にお越しいただき、4年ぶりの対面での日本建築学会大会を安全に楽しんでいただければ、大会実行委員会委員全員の喜びとするところです。
2024年日本建築学会大会(関東)大会委員長挨拶

2024年大会委員長
北山 和宏
来年度の本会大会を担当する関東支部の北山でございます。2023年度の本会大会が近畿支部において執り行われるに当たって、ひと言ご挨拶を申し述べます。
これまで大会の実施に向けてご尽力された近畿支部の大会委員会(谷口徹郎委員長)、大会実行委員会(西山峰広委員長)、および開催校である京都大学の皆さまを始めとする関係各位に深く感謝の意を表します。これだけのマンモス大会を実施することの困難さに思いを馳せるとき、皆さまの献身的なご努力に対して満腔の敬意を抱きます。この大会を成功裏に終えられますように祈念いたします。
さて、四年に渡り猖獗を極めたCOVID-19の猛威も表面上は落ち着き(とは言えヴィールス自体が消えたわけではありませんが)、社会全体が平常化に向かうとともにこれまで以上に発展しようとする機運に溢れています。そのようななかで本年、京都大学で実施される大会は、対面での発表および質疑応答を基本とはするものの、これまでの逼塞生活で強いられたオンライン形式も積極的に活用する方式を採用されました。参加費等の徴収では現金の授受を取りやめる等の新しい試みを実施されています。これらは今後の大会のあり方に対する貴重な先例になることと思います。またメインテーマとして掲げられた「歴史がひらく未来」という標語については、古都京都の歴史性を活かした素敵なネーミングであると思います。伝統ある京都大学吉田キャンパスで歴史を体感しながら皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。
ところで来年度の大会でございますが、2024年8月27日から30日までの四日間にわたって東京の明治大学駿河台キャンパスを主会場として実施する予定です。大会の実施を引き受けていただいた明治大学理工学部建築学科の山本俊哉先生、田中友章先生、酒井孝司先生、小山明男先生を始めとする教員の皆さま、および明治大学の関係各位には感謝の言葉もございません。ありがたいことと思っております。このような心意気に応えるべく、大会実行委員会の皆さまの負担をできるだけ軽減するように努めて参る所存です。なお、来年の大会でも京都大学での運営を参考にして対面およびオンラインを併用する予定です。例年よりは少し早い時期(晩夏とはいえ、多分暑いことでしょう)での開催となりますが、皆さまにはご予定をいただければ幸いです。
今年度の近畿大会が参加される皆さまにとって実り多いものとなることを願いつつわたくしの挨拶を終わります。お読みいただき、ありがとうございます。